様々な制約が設けられている、高卒採用。
学校による斡旋では、決められたスケジュールで就職活動が行われ、1人1社制と言われる慣行が存在したり、履歴書も指定のものがあるなど細かいルールが存在します。
この記事では、高卒での就職を考えている人へ向けて、2025年版(令和7年版)高卒採用のポイントや、注意点をわかりやすくご紹介します!
目次
高卒で就職する3つの方法とは? | 自己開拓・縁故・学校斡旋

高校を卒業と同時に、就職を考えている皆さん。
「さぁ就職活動するぞ!」と思っても、まず何から始めたらよいか、わからない人も多いのではないでしょうか?
まずは、就職の方法を確認しましょう。
自己開拓
自分で求人へ応募し、就職をするのが「自己開拓」と呼ばれる方法です。
大卒での就職などと同様に、自分自身で求職活動を行い、試験や面接を受けて採用に至ります。
縁故就職
縁故就職とは、家族や親類などの紹介で就職を行う方法です。
家族、親類が経営している会社への就職など、親しい人の口利きで就職が決まります。
学校斡旋
学校斡旋とは、学校に届いた求人票から生徒が就職先を選び、学校の推薦を受けて就職する方法です。高卒就職の9割以上が、この学校斡旋によるものとなっています。
学校斡旋は、毎年決まったスケジュールで行われます。
また、独自のルールなども存在しますので、後から慌てないようにしっかりと理解して就職活動を行って行きましょう。
学校斡旋による高卒採用のスケジュール【2025年最新版】

一般の求人とは異なり、学校斡旋による高卒求人は厚生労働省が定めるスケジュールに沿って、採用活動が行われます。
スケジュールは高校生の皆さんの学校生活に、支障が出ないよう設定されていますよ。
令和7年(2025年)のスケジュールはこのようになっています。
企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 ・・・・・・・・ 7月1日
学校から企業への生徒の応募書類提出開始 ・・・・・・・・ 9月5日
(沖縄県は8月30日)企業による選考開始及び採用内定開始 ・・・・・・・・ 9月16日
7月1日の求人票公開から9月5日応募開始までの期間が、高校生のみなさんにとって就職活動が本格化する非常に重要な時期になります。
期末テストでしっかりと結果を残して、夏休みの間に時間をかけての就職活動をおすすめします。
そのためにも高校3年生を迎える頃には、就職のイメージをした上で、7月の求人票の公開を迎えられるとよいですね。
7月1日の求人票の公開後、企業によっては職場見学や、インターンシップを行う場合があります。
実際の職場の雰囲気や、実務を経験できるため、就職した際のイメージも湧くでしょう。
少しでも気になる企業があるようなら、参加することをおすすめします。
また、学校によってはこの時期に、三者面談を行うこともあります。
不安に感じていることや、疑問に感じていることは、先生や保護者に相談すると良いですね。
出典:厚生労働省令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等をとりまとめました。
出典:厚生労働省 就職活動スケジュール(新規高卒者)
高卒採用のルールと注意点|1人1社制とは?

学校斡旋による、高卒採用には「1人1社制」というルールが存在します。
これは生徒1人あたり、求人に応募できる企業は一社とする制度です。
またこの1人1社制の制度においては、原則として内定の辞退はできません。
希望する企業に就職できなかったらどうするの?と思われるかもしれませんが、この「1人1社制」のルールには期間が設けられています。
令和7年でいうと、9月16日の採用試験開始日から、学校斡旋で申し込んだ企業の合否が出るまで、他の企業への応募ができません。
複数社の応募が可能となるタイミングは、都道府県ごとに関係機関の調整により最終的な日程の調整がされます。
1人1社制のメリット
高卒の採用選考において慣行となっている、この1人1社制。
申し込みが1社にしかできないなんて、デメリットしか無いようにも感じられますよね。
内閣府のホームページには1人1社制のメリットとして、以下の点が挙げられています。
・求人が少ない状況下でも多くの生徒に比較的公平に応募の機会を与え、より確実に卒業時までに内定を得ることが可能
・就職活動の長期化による高校教育への影響を考慮し、短期間でのマッチングが可能
・複数社への応募による生徒の身体的・心理的・経済的負担を軽減
・求人企業の立場でも計画的、効率的な採用選考が可能(内定辞退がごく限定等)
しかしながら、この1人1社制には生徒本人の意思が十分に反映されないといった課題もあり、今後見直しされる可能性があります。
現状、秋田県と沖縄県については、9月16日から複数応募が可能となっています。今後も自治体によっては、複数応募を可能にする自治体も増えてくるかもしれません。
出典:内閣府ホームページ 1人1社制をはじめとする高卒雇用慣行の見直しについて
高卒採用を成功に導くために準備すべき3つのこと

みなさんは働いてみたい業界、希望する職業はイメージ出来ていますか?
「何がやりたいのかわからない」
「自分にはどんな仕事が向いているんだろう」
そんな風に、考えている人も多いのではないでしょうか?
具体的な就職先がイメージできている人はもちろん、まだどんな仕事にしようか悩んでいる人にも向けて、高校採用を成功させるためにできることをお伝えしたいと思います。
自分に向いている仕事を確認してみよう
当たり前ですが、世の中にある仕事の内容は全て同じではありません。
人と接することが多い職業もあれば、機械を操作することが多い職業もあります。
椅子に座ったままの職業もあれば、たくさん体を動かす職業もあります。
コミュニケーションが得意な人なら、人と接することが多い職業が向いているでしょうし、黙々と作業をこなすことが好きな人なら、機械を操作する職業がむいているでしょう。
そんな風に、それぞれの仕事の特性から、自分にあった職業を紹介してくれるサイトをご紹介します。
こちらは厚生労働省が公開している自己診断ツールで、次の6つの項目から構成されています。
・仕事価値観検査
・職業適性テスト(Gテスト)
・しごと能力プロフィール検索
・ポータブルスキル見える化ツール
・結果を組み合わせて適職を検索
高校生のみなさんが取り組みやすいのは「職業興味検査」「仕事価値観検査」でしょう。
「職業興味検査」では、具体的な仕事の内容、例えば『自分の店を経営する』ということについて、「やりたい」「やりたくない」「どちらともいえない」に答えることで、どんな職業が向いているかを診断できます。
また関連職業リストとして自分にあった職業が表示され、その仕事の詳しい内容、職業に含まれるこまかな仕事(タスク)や、その仕事に就業するための方法を確認することができます。
「仕事価値観検査」ではあなたが仕事を選ぶ上において、重要視している価値観をはかり、それにマッチする職業を知ることができます。
例えば、「何らかの形で人を支えたり、助けるような仕事がしたい」という質問に対し、
「あてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」
「あまりあてはまらない」「あてはまらない」
この5つの中から、どれか1つを直感で選んでいく形で、診断されます。
まだ働いたことのない高校生でも、なんとなく持っている仕事へのイメージで、職業とのマッチングができますよ。
あまりなじみのない職業も自分に「向いている」として表示されることもあり、世の中の「仕事」への興味も湧いてくるかと思います。
またこちらのjog tagのトップページからは、500を超える職業の仕事の内容や、求められるスキルや知識、労働条件の特徴などを確認できます。
もともと興味のある職業がある人は、どうすればその職業に就けるのかといったことも確認できるため、ぜひ活用してみて下さい。
これらのツールで職業への理解を深めておくことで、インターンなどで実際の現場へ行った際にもより有意義な時間が過ごせることでしょう。
自己分析をしてみよう
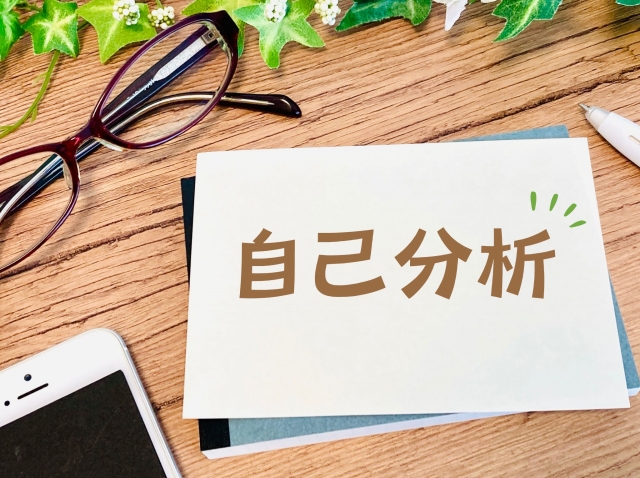
みなさんが、就職しようと考えた理由はなんでしょう?
「職人になりたいという夢があったから!」
そんな風に胸を張って言える人もいるでしょう。
とっても素敵なことです。
けれど中には、「勉強が好きじゃないから」「進学はできないから」「親に言われたから」そんな理由で就職を考えている人もいるのではないでしょうか。
みなさんは、将来どうしたいか、自分がどうなりたいか、考えたことはありますか?
なんとなく、わかっている気がしている自分自身のことを、いま一度振り返って分析してみましょう。
こちらは、厚生労働省が公開している自己分析ワークシートです。
大学生向けではありますが、自己分析のワークシートは高校生のみなさんでも活用できるものになっています。
趣味や特技、成功体験など項目ごとに端的に書いていくだけで、自分という人間を分析できますよ。
改めて書き出すことで、自分が何を考え、将来どうしたいかという事を考えられますし、長所・短所についても再認識することができるでしょう。
それは就職先を検討する際にも重要な情報ですし、これから迎える就職の面接においても大事なポイントになります。
自己分析は、自分を客観的に見つめ直すことができます。
自分の内面に耳を傾けることで、これからどうしたいのか、という問いに答えが見つかるかも知れません。
ぜひ時間のある夏休みの最初に取り組んでみてください。
働くイメージをしっかりとしておく
高卒の離職率は高い、なんて聞いたことはありませんか?
データからも、高卒者は大卒者に比べ仕事を辞めやすい傾向を見て取ることができます。
就職後3年以内の離職率を、厚生労働省のデータから見てみましょう。
新規高卒就職者 38.4%(前年度と比較して1.4ポイント上昇)
新規大学卒就職者 34.9%(同2.6ポイント上昇)
大卒者よりも高卒者の方が、3.5ポイント3年後の離職率が高くなっています。
大卒者に比べ高卒者の方が離職率が高い理由の1つとして言われているのが、準備期間の短さです。学校斡旋での就職を希望する場合、活動の期間は求人票の公開から合否まで、3ヵ月ほどしかありません。
加えて企業から高校生への直接連絡も禁止されており、全て学校を通してのやりとりとなるため、どうしても主体的に行動する場面が少なくなりがちです。
高卒者がどんな理由で辞めているのか、上位の理由をチェックし、事前にきちんと求人票で確認できるところは確認しておきましょう。
離職に至った理由として多いものは、
「人間関係がよくなかった」 26.9%
「賃金の条件がよくなかった」 23.4%
「仕事が自分に合わない」 20.1% (3つまで複数回答)
となっています。
もちろん入社しないとわからない事もありますが、労働条件や職場環境など事前に確認できる内容についてはしっかりとチェックして、働くイメージをしておきましょう。
出典:厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します
出典:厚生労働省 平成30年若年者雇用実態調査の概況
高卒採用試験の流れと履歴書・面接対策【準備のコツ】

就職を希望する企業が決まったら、募集要項に沿って、応募の準備を始めましょう。
高卒採用で使用される履歴書は、一般的に販売されているものではなく「全国高等学校統一応募書類」を使います。(厚生労働省 履歴書)
全国高等学校統一応募書類の記入方法
全国高等学校統一応募書類には、履歴書と調査書があります。
「履歴書」は生徒が記入し、「調査書」は学校側が記入します。
求人票に「手書き入力」「パソコン入力」「手書き入力・パソコン入力どちらでも可」のいずれかの記入方法が明示されているため、それに沿って記入を進めていきましょう。
パソコンでの入力が難しいという人は、先生などに教えてもらいましょう。
履歴書を書く際の注意点
履歴書が手書きと指定されている場合、きれいな文字で丁寧に記入するようにします。誤字や脱字がないよう、事前に何を書くかを下書きしてから清書していきましょう。
間違えた場合は修正テープなどで修正は行わず、新しい用紙に記入しましょう。二重線で訂正する方法もありますが、面接官によい印象を与えるためには新しい用紙に記入する方が望ましいです。
写真は3ヵ月以内に撮影した写真を使用します。
服装はスーツか普段着用している学校の制服を着用し、身だしなみをきちんと整えて撮影します。
撮影は写真館、もしくは証明写真機で行いましょう。スマートフォンで証明写真として撮影できるアプリなどもありますが、ライトや背景など写真の仕上がりが違ってくるため、避けた方が無難です。
好印象を持ってもらえるような履歴書になるよう、先生やご両親にも相談しながら仕上げていきましょう。
企業によっては、卒業証明書、推薦書など別途書類が必要になる場合があります。募集要項の必要書類をしっかりと確認しておきましょう。
高卒採用の試験内容とは
採用試験では、面接や筆記試験、適性検査などが行われます。
企業によって選考の方法が異なるため、こちらも事前に求人票などをしっかり確認して、対策を行いましょう。
ちなみに高卒採用は、書類選考のみで合否を決定することは、認められていません。
面接や作文など、先生などに協力してもらい準備をしておくと安心ですね。
面接の心得。就職は自分自身を売り込むことと知るべし!
就職活動のゴールは、あなたが望む企業に採用をしてもらうことです。
では、どうすれば採用してもらえるでしょう?
就職活動において、売り込むべきは他でもなく「自分自身」です。
集まった学生の中で、自分がこの企業に向いているとアピールするためには、自分がどんな人間で、どういう点で会社に貢献できるかを伝える必要があります。
こう書くとと、なんだかちょっと難しそうに見えますね。
ですが、この記事を読んでいる人の中には高校受験の時、面接を受けた人も多いのではないでしょうか?
中学校時代、バスケ部で主将を務めた人なら、こんな風に自己PRができますね。
「私は周囲の状況を冷静に判断し、仲間に指示を出すことができます」
過去の自分の経験を通して、自分自身がこういう事ができるというアピールができています。
今年で18歳となり、法的に大人となる高校3年生のみなさん。
この区切りの年に、ぜひ、自己分析シートや自分史などを作って、自分自身を見つめなおして下さい。
自分の経験や考えを振り返り、「どんな強みがあるのか」を再認識することで、面接で自分自身を売り込むこともできます。
高校生の魅力は、ズバリ若さと素直さです。
企業は自社の為に育ってくれるやる気のある、若い人材を求めています!
過去の経験などを振り返り、自分のセールスポイントを見つけて、ぜひとも面接でアピールしましょう。
まとめ:高卒就職を成功させるために今できること

人はなぜ、働かないといけないのでしょうか。
もちろん、1つはお金を稼ぐためです。
縄文人のように、自給自足で生きていくならお金は必要ではないでしょうが、現代で生きていくには少なからずお金は必要です。
その他にも社会貢献のためとか、家族のためとか、いくつか理由はあると思いますが、筆者は働く理由を「新しい役割を得るため」だとも考えます。
高校を卒業すれば、高校生という役割がなくなります。
部活を引退すれば、部員としての役割がなくなりますね。
さて、高校を卒業した後、あなたに残る役割は何でしょう。
進学もせず、就職もしなかったら、一日何をして過ごしますか。
毎日が夏休みのような生活は夢のようですが、お金もない実家暮らしは現実的ではないでしょう。
就職を選択し、なにか新しい役割を得ようと思った時、あなたは何がしたいでしょうか。
どんな仕事をして、どんな大人になり、どんな風に生きたいでしょうか。
高校生のみなさんには具体的に考えて、主体的に行動してほしいと思います。
就職は他の誰でもない、あなた自身の未来の選択なのですから。








